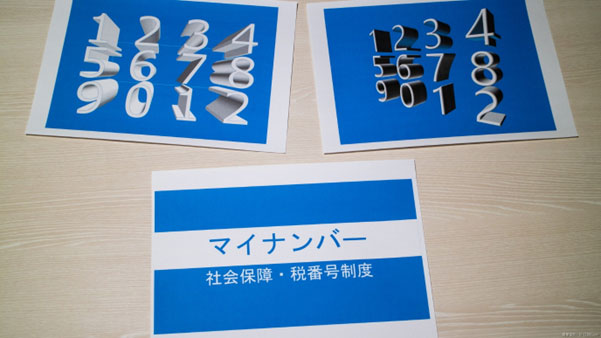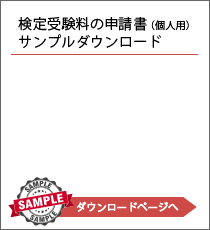マイナンバーの提出は義務?従業員から拒否された場合の企業対応
2025.4.1
マイナンバーの提出は義務?従業員から拒否された場合の企業対応
企業の税金や社会保険の手続きに、マイナンバーの記載が必要になっています。しかし、さまざまな理由からマイナンバー提出を拒否する従業員もいるのではないでしょうか。
この記事では、従業員がマイナンバーを提出することは法律で定められているのかどうかを解説するとともに、従業員に提出を拒否されたときの対応策を紹介します。マイナンバー収集の手順についても解説していますので、参考にしてください。
マイナンバーの会社提出は義務?

結論からいうと、従業員がマイナンバーを会社へと提出することは義務にはなっていません。拒否しても、法令上の罰則が科せられることもないのです。
しかし、社会保障および税の関係書類へのマイナンバーの記入は、関係法令および番号法で義務付けられています。そのため、源泉徴収票および社会保険届出の事務作業時に従業員からマイナンバー情報の提供を拒否されてしまうと、各書類は作成できません。
もしマイナンバーの記載を必要とする書類を作成して従業員が提出を拒否した場合、企業は書類提出先の機関に指示を仰ぎます。
企業がマイナンバーの提出を従業員に義務付けることは可能?

前述したとおり、企業がマイナンバーの提出を従業員に義務付けられません。 なかには、「入社時にマイナンバーを提出しなければならない」と就業規則に記載している企業もありますが、従業員が拒否したからといって提出は強制できません。
しかし、社会保障および税の関係書類にはマイナンバーの記載が義務付けられているため、利用目的を明確に説明したうえで従業員の同意を得て、マイナンバーを提出してもらう必要があります。
なかには利用目的を説明しても、マイナンバーの提出を拒む従業員もいるでしょう。この場合、企業は従業員に対し「従業員のマイナンバーを収集し、社会保険や税の書類に記載することは義務である」と必ず説明しなければなりません。この際、従業員に納得してもらうまで何度も粘り強く説得する必要があるでしょう。
その際になぜマイナンバーの提出を拒否するのか、その理由を確認することも大切です。また、説得する際は以下のポイントを押さえておきましょう。
なかには、個人情報の漏えいに懸念を抱いている従業員も多いでしょう。彼らの不安を払拭するためにも、マイナンバーを適切に保管していることは納得してもらえるまで、明確かつ丁寧に説明しなければなりません。
それでも提供を拒否された場合は、提供を求めたにもかかわらず拒否された旨を書類に記載します。マイナンバーの提出を求めた記録が確認できれば、企業の義務違反ではないことを証明できるでしょう。そのうえで、提供先の機関への指示を仰ぎましょう。
企業がマイナンバーを収集しなければならない理由
企業が従業員のマイナンバーを収集する目的は、「税金の手続き」と「社会保険手続き」のふたつです。それぞれについて解説します。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 保険証の発行が遅れる可能性がある
- 医療機関を受診した際に、健康保険証の資格確認に支障が出る場合がある
- 戸籍謄本や住民票を取得する際に費用が発生する
- マイナポータルを活用したサービスが受けられない
- 協会けんぽの場合
自社が協会けんぽに加入している場合は、マイナンバーがなくても基礎年金番号で手続きを進められます。しかし、マイナンバーを記載した場合は住所の記載は必要ありませんが、基礎年金番号を記入する場合は、住所を記載しなければなりません。また、家族を扶養に入れる場合は、扶養者と被扶養者の続柄を確認するために、住民票などの本人確認書類の添付が必要です。 - 健康保険組合の場合
自社が健康保険組合に加入している場合は、組合によって対応が異なるため、問い合わせて指示を仰ぎましょう。多くの組合ではマイナンバーがなくても手続きが可能ですが、なかにはマイナンバーが必須のところもあるため注意が必要です。 - 福祉や保険といった社会保障にかかわる事務
- 源泉徴収票や支払調書などの事務
- 地方税にかかわる事務
- 防災にかかわる事務
- マイナンバーカード
- マイナンバーを記載している住民票の写し
- マイナンバー通知カード
- 1点のみでよいもの
免許証・パスポート・在留カード・身体障害者手帳 - 2点以上必要なもの
年金手帳・公的医療保険の被保険者証・児童扶養手当証書・年金手帳 - 組織的安全管理措置
マイナンバーの取り扱いに関する規定を明確にし、運用手段を整備する - 人的安全管理措置
マイナンバー事務担当者を対象とした研修とマイナンバーを適切に利用しているかどうかの確認を定期的に実施する - 物理的安全管理措置
マイナンバーを取り扱う区域を適切に管理する - 技術的安全管理措置
マイナンバーへのアクセス制御やセキュリティ対策を実施する
税金手続きのため
企業は従業員の税金関連の手続きをする際に、必要書類にマイナンバーを記載しなければなりません。具体的には、源泉徴収票および支払調書にマイナンバーを記載する必要があります。
これは、税務署に提出する書類に関しての場合であり、従業員に交付する源泉徴収票には記載する必要はありません。もし従業員に交付する源泉徴収票にマイナンバーを記載してしまうと、ほかの従業員の目に触れたり、郵便事故でほかの人の所に届いてしまったりしたことがきっかけで、個人情報の漏えいにつながる恐れがあります。そのため、従業員への源泉徴収票には記載しないようにしましょう。
社会保険手続きのため
社会保険の手続きをする際にも、企業は従業員のマイナンバーを収集しなければなりません。具体的には、以下の手続きの際にマイナンバーが必要です。
従業員の被扶養者に異動があった場合や毎年7月の算定基礎届を提出するとき、従業員が育児休業を取得したときなどには、健康保険および厚生年金保険の届出書類にマイナンバーを記載しなければなりません。
雇用保険に関しては従業員が就職したときや退職したときには、資格取得届や資格喪失届を提出しなければなりませんが、そこにはマイナンバーを記載する必要があります。そのほかにも、従業員が高年齢雇用継続給付を受けようとするときや、育児休業給付金・介護休業給付金を受ける場合に記載する雇用保険の届出書類にも、マイナンバーの記載欄が設けられています。
従業員はマイナンバーを提出せずに社会保険に加入できる?
マイナンバーを提出しなくても、社会保険への加入は可能です。しかし、企業は従業員に以下の不具合が生じる可能性があることを伝えておく必要があります。
また、健康保険証とマイナンバーカードが一体化され、2024年12月2日以降は現行の保険証は新規発行されなくなりました。そのため、従来の保険証を紛失してしまっても、新たな保険証は発行されないことも周知しておかなければなりません。そのうえで、マイナンバー提出を拒否された場合は、次の手続きをとりましょう。
従業員のマイナンバーを収集する流れ
従業員のマイナンバーは一般的に以下の流れで収集します。
まずはマイナンバーの利用目的を周知したうえで、マイナンバー情報を収集します。場合によっては従業員だけでなく、従業員の扶養家族や株主、税理士などの個人取引先のマイナンバー情報を収集しなければならないときもあるでしょう。その際にも必ず利用目的を通知し、同意を得たうえで収集しましょう。
1.利用目的を明確に周知する
まずは従業員に、どのような業務で利用するのかを周知しましょう。この際口頭のみで通知するのではなく、利用目的通知書や同意書などを配布して、従業員が確実に目的を理解できるようにしてください。質問がある場合は、応えられるようにしておきましょう。従業員の不安や疑問に回答する機会を設けておくと親切です。ちなみに、法律で定められているマイナンバーの利用範囲は以下のとおりです。
上記の目的以外には決して使用しない、ということも必ず明記しましょう。
2.従業員のマイナンバーが記載された書面を受けとる
続いて、従業員のマイナンバーが記載されている書面を収集します。この際、マイナンバーの収集担当者を定めておきましょう。不特定多数の人間がマイナンバー収集業務に携わると、情報漏えいの要因になる恐れがあるため注意してください。
やむを得ず担当以外の従業員を経由してマイナンバーを受け取る場合は、できる限り速やかに回収します。また、経由した従業員の手元に情報が残らないように徹底してください。従業員だけでなく、扶養家族のマイナンバーが必要な場合は、従業員本人が収集して担当者へと提出します。
マイナンバーの確認には、以下の書類を参考にします。
このうちマイナンバーカードは本人確認書類も兼ねられます。
3.従業員の本人確認を行う
企業がマイナンバーを収集する際、本人確認は必須です。本人確認は以下の書類で行います。
扶養家族のマイナンバーも収集している場合は、従業員自身の責任のもとで番号確認、および本人確認を行うことになっています。
4.収集した書類等を適切に保管する
収集したマイナンバーは、適切に管理する必要があります。具体的には、以下の安全管理措置を講じましょう。
また、マイナンバーが記載されている書類のうち、保管義務がないものや保管期間が過ぎた書類は速やかに廃棄しましょう。マイナンバーを保管していたデータを削除したり、マイナンバーを保存していたパソコンなどを破棄したりした場合は、その旨を記録しておかなければなりません。廃棄業者に委託した場合は、廃棄証明書を作成してもらいましょう。
マイナンバー提出義務に関するよくある質問
最後に、マイナンバー提出義務に関するよくある質問を、Q&A形式で紹介します。
Q.アルバイトでもマイナンバーを提出する必要があるの?
A.正社員に限らず、アルバイトやパートタイマーに関しても、社会保障や税金の手続きに関してマイナンバーを提出しなければなりません。しかし、前述したとおり、企業はマイナンバーの収集義務を負いますが、アルバイトやパートタイマーといった従業員は提出する義務はありません。そのため、マイナンバーを提出しなかったからといってクビになるなどの罰則を科せられることはありません。
Q.従業員だけでなく、家族のマイナンバーも提出する必要がある?
A.税金や社会保険の手続きには、従業員だけでなく、扶養家族に通知されているマイナンバーが必要です。扶養家族がいる従業員は、家族のマイナンバーも提出しなければなりません。ただし、扶養家族の番号確認と本人確認は、企業ではなく従業員本人が行います。扶養家族以外の家族のマイナンバーは、提出しなくてもかまいません。
まとめ
企業は税金や社会保険の手続きの際、必要書類には従業員のマイナンバーの記入が必須です。しかし、従業員のマイナンバー提出は義務ではありません。そのため、拒否されても罰則を科すことはできません。
マイナンバーを提出してもらえないと、手続き上不具合が起こる可能性があるため、できる限り従業員には提出してもらいましょう。従業員の協力を得るには、マイナンバーの使用目的や保管方法を明確に周知しなければなりません。安全対策を徹底して、従業員の不安を払しょくすることも大切です。担当者が、マイナンバーやセキュリティ業務に関する正しい知識を身につけておきましょう。