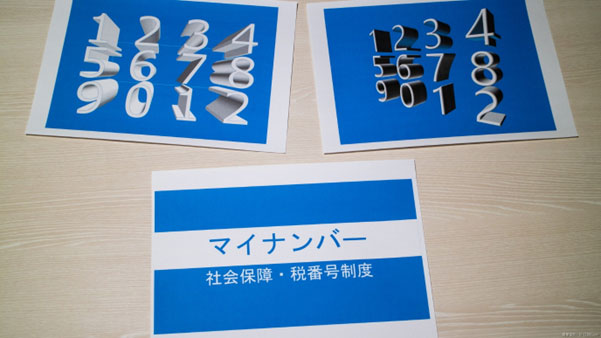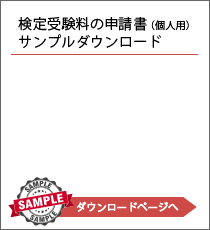マイナ保険証とは?メリットや注意点、移行時に企業が実施すべき対策も解説
2025.4.1
マイナ保険証とは?メリットや注意点、移行時に企業が実施すべき対策も解説
2024年12月2日以降、「マイナ保険証」への移行が開始され、従来の保険証の新規発行が終了しました。しかし、マイナ保険証とはいったいどのようなものなのか、移行に関して企業はどのような対応が必要なのかがわからないという方も多いのではないでしょうか。
2本記事では、マイナ保険証の概要をわかりやすく解説するとともに、マイナ保険証のメリットおよび利用時の注意点、マイナ保険証への移行に関して企業が取るべき対応について紹介します。
マイナ保険証とは?

マイナ保険証とは、健康保険証の機能を紐付けたマイナンバーカードのことです。医療機関を受診したり、薬局で薬を購入したりする際にマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。利用する際は、医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで受付するのが特徴です。
現在、従来の保険証からマイナ保険証への移行が進められており、2024年12月2日以降は従来の保険証の新規発行は行われていません。しかし、2024年12月2日時点で有効な保険証を持っている場合は1年間の経過措置が設けられているため、そのまま使用できます。今後、マイナ保険証を持っていない人には、健康保険証代わりに利用できる「資格確認書」が送付される予定です。しかし、医療機関は徐々にマイナ保険証を基本とする仕組みへと移行しているため、できるだけ早めにマイナ保険証へ登録することをおすすめします。
マイナンバーカードを持っている場合は、医療機関や薬局でマイナ保険証の登録が可能です。そのほか、政府が運営するオンライン窓口「マイナポータル」やセブン銀行のATMでもマイナ保険証の登録ができます。
マイナ保険証のメリット

ここからは、マイナ保険証を利用するとどのようなメリットがあるのかを解説します。
マイナンバーカードは、「顔写真付きの身分証明書」として使用可能です。マイナンバーカードには、以下の情報が記載されています。
マイナ保険証に登録することで、確定申告の医療費控除が簡単にできるようになります。医療費控除とは、1年間に自分自身および家族が支払った医療費の合計が一定額を超えた場合、所得税の還付が受けられる制度です。
医療費控除を受けるために、これまでは自分で医療費の領収書から「医療費控除明細書」を作成し、確定申告で提出しなければなりませんでした。しかし、マイナ保険証に登録してマイナポータルと国税に関するさまざまな手続きをオンラインで行う「e-tax」を連携すれば、1年間の医療費が自動入力できます。
面倒な計算もいりませんし、医療機関でもらった明細書を1年間保管しておく必要もないため確定申告がスムーズになるでしょう。
マイナ保険証を利用すれば、従来の保険証や資格確認書を利用するよりも初診料が20円、再診料が10円安くなります。それぞれの金額はさほど大きくありませんが、長く通院することになった場合や、持病があって定期的に診察を受けなければいけない場合は、トータルすると負担が安くなるでしょう。
従来の保険証を利用している場合は就職や転職、引っ越しの際に保険証の切り替えをしなければなりませんが、マイナ保険証ではその必要がありません。そのまま引き続きマイナ保険証の利用が可能です。
また、後期高齢者医療制度や国民健康保険を利用している場合、これまでは定期的に保険証を更新しなければなりませんでしたが、その必要がなくなります。
切り替えや更新で保険証が手元にないときに医療機関を受診すると、自己負担額が10割になります。後日保険証を提示したり、「療養費」の請求をしたりすれば払い戻してもらえますが、何度も医療機関を訪ねたり、手続きをしたりと手間がかかります。
その点マイナ保険証なら更新や切り替えが不要なため、面倒な手続きもなく、環境が変わっても常に保険証が手元にあるため安心です。
マイナ保険証に登録しておくと、簡単に高額療養費制度が利用できます。高額療養費制度とは同じ月に高額な医療費が必要となった場合、一定の額を超えた分は後で払い戻しされる制度です。
事前に医療費が高額になることがわかっている場合は、「限度額適用認定資格」を申請すれば、限度額以上の医療費を支払う必要はありません。しかし、申請が間に合わなければ、全額支払う必要があるため負担が大きくなりますし、通院しながら限度額適用認定資格を申請するのは面倒なものです。
その点マイナ保険証に登録しておけば、医療機関がシステム上で限度額適用認定資格を確認できるため、手続きをしなくても高額療養費制度が適用されます。
マイナ保険証利用時の注意点
さまざまなメリットがあるマイナ保険証ですが、利用時にいくつかの注意点があります。詳しく解説しますので、参考にしてください。
- ひとり親家庭医療費助成
- 障害者医療費助成
- 小中学生医療費助成
- 特定医療費(指定難病)受給者証
有効期限がある
マイナンバーカードには有効期限があり、期限が切れてしまうと保険証としても利用できません。マイナンバーカードの有効期限は、10年(未成年は5年)です。
また、マイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限は5年となっています。そのため、マイナンバーカードの有効期限が残っていても、電子証明書の期限が切れている場合は使用できません。
有効期限が切れる3か月ほど前になると、自宅に「電子証明書更新のお知らせ」が郵送されます。うっかり期限が切れていて必要なときに利用できなかった、ということにならないようにお知らせが届いたらできるだけ早く更新手続きを行いましょう。更新手続きは、原則として各自治体の窓口で行います。
公費負担医療制度と紐付けされていない
マイナ保険証は、公費負担医療費制度と紐付けされていないため、対象の方は注意が必要です。主な公費負担医療制度には、以下のものがあります。
これらの公費を持っている方が医療機関を受診する場合、マイナ保険証とは別にそれぞれの証明書や受給者証を提示する必要があります。そのため、公費を持っている方は「従来の保険証との違いがあまりわからない」と感じるかもしれません。
高齢者には使いづらい
マイナ保険証は、高齢者にとって使いづらいと感じるかもしれません。医療機関でマイナ保険証を利用する場合は顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証を入れ、顔認証もしくは4桁の暗証番号を入力して本人確認を行います。
機械に不慣れな高齢者の場合、マイナ保険証を入れる場所がわからない、顔認証に手間取る、暗証番号を忘れてしまった、というケースがあるかもしれません。本人確認に手間取っているうちに、後ろに順番待ちの列ができてしまうとますます焦ってしまうでしょう。
その結果、「これまでの保険証のように、受付に提出すればOKにしてほしい」と感じてしまう人も出てくる可能性があります。
機器に不具合があると使えない
マイナ保険証のシステムやカードリーダーに不具合が生じると、マイナ保険証が使えなくなる恐れがあります。医療機関もマイナ保険証に移行してから日が浅いため、トラブルが起こった際の対処に慣れていないところが多いです。その結果、窓口での対応が遅れてしまうこともあるでしょう。
また、機器のトラブルが起きてマイナ保険証が使えない場合、従来の保険証の提示を求められたり、専用の用紙に必要事項を記入したりと手続きが面倒になる可能性があります。
情報漏えいのリスクがある
マイナ保険証を紛失したり、カードリーダーに置き忘れたりして悪意のある第三者の手に渡ってしまうと、個人情報が漏えいするリスクもあります。紛失や盗難には十分気をつけましょう。
万が一紛失してしまった場合は、すぐに「マイナンバーカード総合窓口」に電話をして、指示を仰いでください。マイナンバーカード総合窓口は、24時間365日受付対応しています。
マイナ保険証への移行で企業が実施すべきこと
従来の保険証からマイナ保険証へと移行するにあたり、いくつか企業で実施すべきことがあります。いったいどのような対応が必要なのか、わかりやすく解説します。
従業員情報を適切に管理する
従来の保険証からマイナ保険証への切り替えは、企業が対応するわけではありません。従業員一人ひとりが個人で行います。また、マイナ保険証へと切り替えるには当然マイナンバーカードが必要です。
そのため、企業はマイナンバーカードを持っていない従業員、およびマイナ保険証への登録を済ませていない従業員などの情報を管理しなければなりません。
2024年9月、事業主宛てに被保険者資格や基本情報を記載した資格情報のお知らせが送付されています。それを活用してマイナ保険証に登録していない従業員を確認し、対応を進めましょう。資格情報のお知らせには重要な個人情報が記載されているため、外部に漏えいしないように管理を徹底する必要があります。
従業員のサポート体制を整える
マイナ保険証への登録方法がわからない従業員のために、サポート体制を整えましょう。具体的には、マイナ保険証への登録手順を具体的にわかりやすく記した社内報を配布したり、マイナ保険証登録に関する疑問や不安を解消するために個別相談会を開催したりします。
デジタル機器に不慣れな従業員にとっては、マイナポータルによるマイナ保険証登録などのハードルは高いかもしれません。そのような人たちにも、具体的に操作方法を教えられるような体制を構築しましょう。
デジタルツールを導入する
マイナンバー管理ツールなどのデジタルツールを導入してデータを一元化し、スムーズな情報管理を行うことも重要です。また、マイナンバー管理ツールを会計システムに連携すれば、マイナンバーに紐付いている従業員の社会保険や所得税が自動入力されるため、給与計算や年末調整が簡素化されるでしょう。
マイナ保険証への移行をきっかけにデジタルツールを積極的に活用することで、マイナンバーの管理だけでなく、さまざまな業務の効率化が図れます。
セキュリティ対策を整える
マイナンバーは重要な個人情報のため、法令に基づいて厳重に管理しなければなりません。従来のツールではセキュリティ面に不安がある場合は、高性能なセキュリティを搭載しているツールを導入するなど、適切に管理できる体制を整えましょう。
デジタルツールを導入しない場合でも、マイナンバーをどのように管理するか、管理担当者はだれにするかなどの取り扱い方法を明確にし、個人情報が漏えいしないようにしっかり対策をします。
まとめ
マイナ保険証には正確で精度の高い医療が受けられる、確定申告などの手続きが簡単になる、などのメリットがあります。しかし、マイナ保険証への登録は個人で行わなければなりません。企業は従業員がスムーズにマイナ保険証の登録ができるようにサポート体制を整えたうえで、個人情報を適切に取り扱うためのセキュリティ対策を行いましょう。マイナ保険証への移行を円滑に行うには、マイナンバーおよびマイナ保険証に関する正しい知識を有することが大切です。
全日本情報学習振興協会が実施している「マイナンバー実務検定」は、マイナンバー制度に対する正しい知識を有し、適正な取り扱いをするための検定試験です。試験を受けることで、業務に必要なマイナンバーの正しい知識が身につくでしょう。