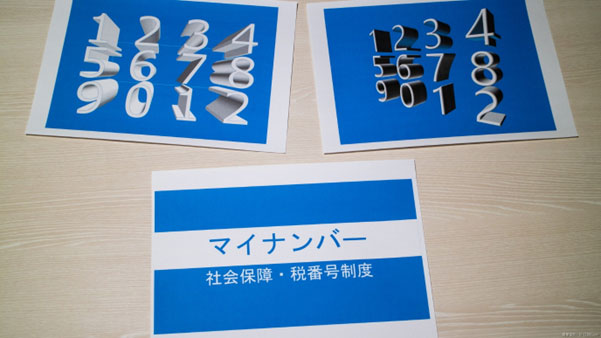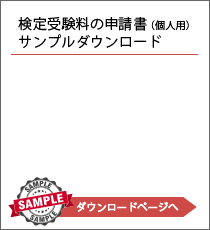マイナンバーカードを作成するメリットは? 実際の活用例で紹介
2025.4.1
マイナンバーカードを作成するメリットは? 実際の活用例で紹介
「マイナンバーカードを作ったけれど、何に利用するのかわからない」「マイナンバーカードを作るのが不安」という方は多いのではないでしょうか。この記事では、マイナンバーカードのメリットや便利な活用方法、注意点をわかりやすく解説します。マイナンバーカードの申請方法についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
マイナンバーカードを作成するメリット4つ

マイナンバーカードを作成することで、さまざまなメリットを得られます。ここでは、代表的なメリットについてわかりやすく解説していきます。
マイナンバーカードは、「顔写真付きの身分証明書」として使用可能です。マイナンバーカードには、以下の情報が記載されています。
マイナンバーカードは公的な身分証明書として、銀行の口座開設や本人確認に使用できます。運転免許証を取得していない、返納してしまったなどの理由で、顔写真付きの身分証明書を持っていない人はマイナンバーカードが重宝します。
マイナンバーカードは、健康保険証として利用できます。マイナンバーカードを保険証として利用することで、過去に処方された薬や検診の情報を病院や薬局にスムーズに共有できます。
また、行政のオンライン窓口「マイナポータル」とマイナンバーカードを連携すれば、確定申告の際に医療費控除が自宅で簡単にできるようになるメリットもあります。
コンビニで公的書類の発行ができるようになるのも、マイナンバーカードの大きなメリットのひとつです。マイナンバーカードを利用して、コンビニで発行できる各種書類は以下のとおりです。
これまで各種証明書を発行する場合は、市区町村の役所や役場での手続きが必要でした。しかし、マイナンバーカードを取得することで、近くのコンビニで発行できるようになります。
マイナンバーカードを取得すれば、わざわざ役所や役場に行かなくても各種契約および手続きができます。主な契約・手続きは以下のとおりです。
マイナンバーカードを持っていれば、以下の子育てに関する手続きがオンラインでできます。
これまで子育てに関する各種手続きは、市区町村の役所や役場に出向いて行う必要がありました。近くに役所がない場合、子育ての合間に時間をかけてわざわざ役所まで出向かなければならないという人も多く不便です。しかし、マイナンバーカードを取得すれば、自宅で隙間時間に申請できるようになります。
マイナポータルの利用者登録を事前に行っておけば、マイナンバーカードを使って自宅で簡単に確定申告ができます。マイナンバーカードとマイナポータルを連携すれば、確定申告に必要な情報のデータを一括取得できるだけでなく、申告書の該当項目も自動入力が可能です。面倒な計算も必要ありません。
マイナンバーカードを取得すれば、転出届がマイナポータルからオンラインでできるようになります。転入届は転入先の市区町村に出向いて手続きする必要がありますが、マイナポータルで事前に来庁予定を連絡できます。
また、来庁の際に必要な書類などをマイナポータルから確認できるため、従来よりも転入届の手続きがスムーズになるでしょう。
金融機関に持っている銀行口座を給付金受取口座として、マイナンバーとともに登録しておくと、給付金の受取手続きがスムーズになります。これまで給付金の申請・受取時は、申請書類に口座番号を記載したり、通帳の写しを添付したりしなければなりませんでした。しかし、口座登録することで、これらの確認作業が一切不要になります。
マイナンバーカードを利用すれば、オンラインでパスポートの更新申請ができます。また、一部の自治体ではパスポートの新規取得、氏名および本籍地の変更、紛失届の申請も可能です。ただし、パスポートの受取は、窓口対応になるため注意しましょう。
マイナンバーカードの便利な活用事例
マイナンバーカードを持っていれば、高額療養費制度の手続きが簡単に行えます。高額療養費制度とは、医療機関および薬局の窓口で支払う金額が1か月の上限を超えると、超えた金額が支給される制度です。
従来の保険証で窓口の負担額を上限に抑えるには、事前に「限度額適用認定証」を申請する必要がありました。もし申請が間に合わなければ、一度全額を支払ったうえで支給申請書を提出しなければなりません。しかし、マイナンバーカードを保険証として利用すれば、限度額適用認定証を申請しなくても高額療養費の限度額を超える支払いは免除されます。
また、マイナポータルとねんきんネットを連携すれば、今までの年金の支払額や受給見込み額がいつでもスマホやパソコンから確認できます。さらに、保険料の免除や猶予、国民年金加入へのオンライン手続きが可能です。
マイナンバーカード利用する際の注意点
各種手続きが簡素化できたり、オンラインでできたりするためとても便利なマイナンバーカードですが、利用時にいくつか注意したいことがあります。それぞれ詳しく解説します。
1.個人情報漏えい
マイナンバーカード作成時に登録した個人情報が漏えいするリスクは、残念ながらゼロとはいえません。なかには個人情報漏えいを懸念して、マイナンバーカード作成に二の足を踏んでいる方もいるでしょう。
しかし、マイナンバーカードに搭載されているICチップには、口座番号や年金情報といったプライバシー性が高い情報は登録されていません。また、マイナンバーカード自体に、悪用やなりすましを防止するための特殊な加工が施されています。ICチップの読み取りには、カード作成時に申請した4桁の暗証番号が必要です。一定回数暗証番号を間違えるとロックされ、解除するには本人が手続きしないといけません。さらにICチップを不正に読みだそうとした場合は、自動で壊れる仕組みになっています。
このように、マイナンバーカードには個人情報漏えいを防ぐためのさまざまな対策が実施されているため、プライバシー情報が流出する危険性は低いといえるでしょう。
2.紛失や盗難
マイナンバーカードを持ち歩く機会が増えれば増えるほど、紛失や盗難のリスクが高まります。もし、カードを紛失したり盗難にあったりしたら、速やかにマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡し、マイナンバーカード利用停止の手続きを行いましょう。マイナンバー総合フリーダイヤルは利用停止手続きに限り、24時間365日受付対応しています。
また、警察に行って紛失届や盗難届を出すことも大切です。この際、受理番号をメモ等に控えて市区町村に届出すれば、再発行の手続きができます。
3.有効期限と更新手続き
マイナンバーカードには有効期限があるため、失効しないように注意しなければなりません。有効期限は18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日までです。有効期限が近づいてきたら、自宅に「有効期限通知書」が送付されます。通知書が届いたら、以下の方法で更新手続きが可能です。
うっかり手続きを忘れてマイナンバーカードの有効期限が切れてしまうことがないように、通知書が届いたら早めに手続きするのがおすすめです。
マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの申請から受取までは、以下の流れで行います。
1.マイナンバーカードを申請する
2.自宅に郵送で「交付通知書」が届く
3.指定の交付場所にてマイナンバーカードを受け取る
マイナンバーカードの申請は、スマートフォン・パソコン・郵送・証明用写真機でそれぞれ申請できます。ここからは、各申請方法についてわかりやすく解説します。
スマートフォンからの申請
1.QRコードを読み取る
まずは「マイナンバー交付申請書」に記載されているQRコードを読み取ります。表示されたURLをタップするとオンライン申請サイトにつながります。利用規約および個人情報の取り扱い、年齢確認に同意しましょう。
2.メールアドレスを登録する
同意ボタンをタップすると、メールアドレスの登録画面が開きます。画面上には「申請書ID」が自動登録されているので、「メール連絡用氏名」に氏名、「メールアドレス」に連絡用のメールアドレスを正確に記入します。その後、画像認証の欄に表示された英数字を正確に入力してください。
3.顔写真を登録する
スマホで撮影した写真をアップロードします。申請に使用する顔写真は、6か月以内に撮影したものに限ります。カラー・白黒どちらでも構いません。ただし、横を向いているものや背景がある写真、鮮明でない写真などは登録できないため注意しましょう。
4.申請情報の登録
顔写真の登録が終わったら生年月日の入力、点字表や電子証明書の発行希望の有無を確認すれば、登録完了です。
パソコンからの申請
続いて、パソコンからの申請方法を紹介します。
1.メールアドレスの登録
パソコンのオンライン申請サイトにアクセスし、スマホで申請するWEBサイトと同じく利用規約および個人情報の取り扱い、年齢確認に同意してください。その後で、「申請書ID」「メール連絡用氏名」「メールアドレス」をそれぞれ正しく入力します。
2.顔写真の登録
登録したメールアドレスに通知が届くので、そこに記載されているURLをクリックして、「申請者専用WEBサイト」にアクセスします。その後、6か月以内に撮影した顔写真をアップロードし登録をしてください。
3.必要事項の登録
生年月日、電子書籍の発行及び氏名の点字表記の希望有無を入力したら、登録完了です。
郵送申請
マイナンバーカードはオンライン以外に、郵送での申請もできます。ここからは、郵送で申請する際の手順を紹介しましょう。
1.必要事項を記載
郵便で届いた「個人番号カード交付申請書」の内容に従って、必要事項を記入します。
2.顔写真を貼る
6か月以内に撮影した顔写真をプリントアウトし、交付申請書の所定の位置に貼り付けます。使用可能な顔写真の条件は、オンラインでアップロードするものと同じです。
3.専用封筒に入れて郵送する
必要事項をすべて記入したら、内容に間違いがないかを確認し、送信用の封筒に入れてポストに投かんします。送信用封筒は、個人番号通知書もしくは通知カードに同封されています。交付申請書や送信用封筒を紛失した場合は、「マイナンバーカード総合サイト」からダウンロード可能です。
証明用写真機からの申請
街中にある証明用写真機を使い、申請も可能です。手順は以下のとおりです。
1.モードを選択する
交付申請書を持参し、タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択して入金し、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。
2.顔写真を撮影する
画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。証明写真機は、種類により申請できるものとできないものがあるため、事前に確認しておきましょう。
いずれの方法で申請しても、受取までにおよそ2か月程度かかります。
まとめ
マイナンバーカードを取得すると顔写真付きの身分証明書として活用できたり、さまざまな手続きがオンラインからできるようになったりと、さまざまなメリットがあります。一方で、個人情報の漏えいや、紛失・盗難といったリスクも否定できません。マイナンバーカードを作成するのが不安という方は、マイナンバー制度やマイナンバーカードについて調べて、理解することで不安が払拭されるかもしれません。
今後も、マイナンバーカードについては、さまざまな新しい情報が更新されると予想されます。常に情報をチェックして、便利に活用できるようにしておきましょう。